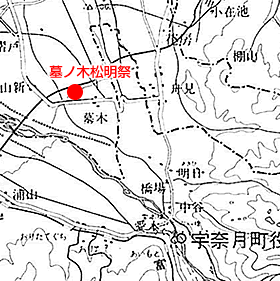|
墓ノ木松明祭
(はかのきたいまつまつり) |
|
地区
|
入善町
|
地域区分
|
扇頂
|
テーマ
|
2
|
分野
|
民族
|
|
場所
|
入善町墓ノ木 |
|
所有者・管理者
|
松明祭保存会会長(墓ノ木地区区長兼任) |
|
電話番号
|
区長宅 |
 入善町・無形文化財(昭和52年4月1日指定)。 入善町・無形文化財(昭和52年4月1日指定)。松明祭は江戸時代中頃、堤防や堰を洪水から守るために、松明の灯のもとで村中の男たちが、徹夜ではたらいたことが起源だといわれている。今では毎年10月13日に行われており、水神に感謝し豊作と息災を祈る意味を持つ。 松明の大きさは高さ4m、直径1.2m、重さ700kgの巨大なものである。これを前後おのおの6人で担ぎ、その両側にバランスを保つためのトラ縄持ちが2人づつつく。 午後7時頃神明社の前で、神官の手によって御神火が2本の大松明に灯され、笛・太鼓と共に米吊り音頭に合わせて行列が始まる。神明社から800m先の水護神社まで約1時間半かけて練り歩いて着く。 演じ色の法被姿の担ぎ手が夜空を焦がす炎と飛び散る火の粉を浴びて、大松明を振立てながら進む姿は勇壮そのものである。水護神社に運ばれた大松明は、子供たちが持ち歩いた小松明とまとめて燃やされて祭は終わる。 松明祭がいつ頃から始まったかははっきりしないが、古老の話によると江戸時代末期からではないかと言われている。 (黒部川扇状地研究所研究員記) |
|
|
|